皆さん、おはようございます。漢仁です。
ご無沙汰して申し訳ございません。今日も一筆入魂でいきます!
新入社員の研修がいまピークですね。
私も「忙しい」なんて言葉が生ぬるいほどで体があと3つくらい欲しいです。
コロナ禍で採用した学生を採用取り消しにする企業が増えてますね。
残念なことですが生き残りを賭けて企業も必死です。
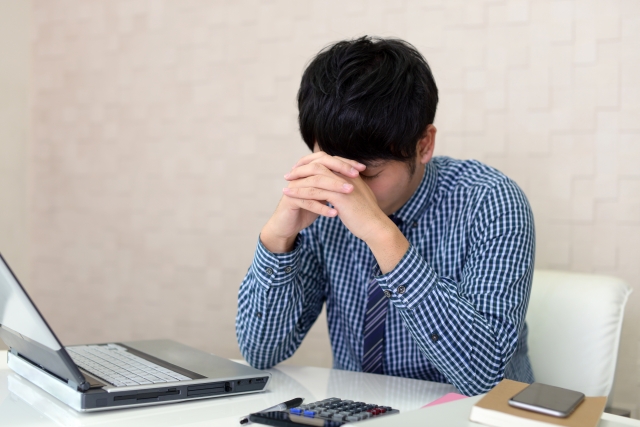
さて、新入社員研修を机上でのみ行う会社もあれば、机上では研修を行わずに先輩社員によるOJTに力を入れる会社があります。
確かに先輩社員の働きぶりを見せて真似させると見様見真似で一番早く仕事のやり方を覚えるというメリットがあるようです。
どの社員にどの新人を付けるかという点が重要になってきますが、全ての新人のOJTにおいて共通して言える重要なポイントがあります。
それは新入社員が先輩社員を見て何を感じているかという「受け止め方」を把握することです。
教える方は普段の仕事を一生懸命見せるのですが、それを見た新入社員が先輩の仕事をどういう風に見て何を感じたのか?
そこが最も重要になってきます。
同行した先輩の報告だけを鵜吞みにせず、新人さんがそれをどう受け止めたのか、必ずフィードバックさせて下さい。
出来れば日報や報告書ではなく、目を見てちゃんと会話して聞き取ってあげる方が効果的だと思います。
そのフィードバックを会社の方向性に照合し、認識の修正やより詳細な細部に亘る指導が必要かどうか、この先どう言った指導をするべきかを判断する材料にすることが出来ます。
先輩がどうやって目を盗み仕事を怠けているか⁉という点に目が行くと、必然的に新入社員もバレないように手を抜くにはどうすればいいか⁉という要領ばかりを真似ようとします。

そこで気を付けたいポイントは、OJTの担当社員を代えること。
色んな先輩につくことで新入社員は情報を総合的に判断しようとします。
つまり仕事というものを画一的断片的に判断するのではなく、重要な部分とさほど重要でない部分のメリハリを理解した上で、手の抜き方を合理的に学び認識するようになるのです。
手を抜かない社員が良いのは言うまでもありませんが、人間はずっと全力を尽くすことはできません。
正確には緊張と緩和ですが、適度に手を抜かないと息が詰まるからです。

ベストな状態を保つために休息を挟むことがより良い成果に繋がります。
OJTにより伝えたいことを全部伝えるのではなく、合間合間にどう思うか意見を聞いてみることで新入社員の感じ方をその都度把握することができます。
詰め込み過ぎず時には肩の力を抜ける環境づくりを大切にされることをお奨めします。
仕事帰りに呑みに行ったり、レクリエーションに誘ったりするのも効果的です。
コミュニケーションを上手に図ることが出来れば、新入社員の現時点での仕事に対する意気込みやモチベーションの状態を把握することが出来ます。
上手に育てるためには「新入社員の意見を聞く」つまりアウトプットさせることに力を入れると自ずと自分の意見をちゃんと言える社員に育ってくれると思います。
私はそのことをこの本から学びました。人を育てるということがどれほど崇高なことかこの本を読まなければこの道に進んでいなかったかも知れません。
私の尊敬する人物で、現在の大阪教育大学(旧大阪天王寺師範学校)で選任講師をされていた教育者を育てる教師「森信三先生」の著書です。
ともすれば一方通行になりがちな教育というものについて、答えは相手が持っているということを理解し聞き出してやることも教える側の使命であると仰ってます。
さらに・・・
「やってみて言って聞かせてさせてみて誉めてやらねば人は動かじ」
第26、27代連合艦隊司令長官、山本五十六のあまりにも有名な名言ですが、現代社会の若者に対しては褒める前に「それをやってみてどう思ったか?」を加えれば完璧だと思います。

さらにその名言の続きにもあるように「話し合い、耳を傾け承認し、任せてやらねば人は育たず」「やっている姿を感謝で見守って、信頼せねば人は実らず」
例え相手が新入社員であっても、一人の人間として尊重し承認することで、信頼されたことに喜びを感じ、自信を持ち、自ら率先して行動する人になってくれると思います。
私が右も左もわからない新入社員だった頃、お前ならできる!信頼してるぞ!思いっきりやってみろ!そう言って背中を押してくれる先輩や上司がいたことを思い出し、自分もそういう存在でいたいといま思うようになりました。
やはりOJTはお手本になる人が重要ですね。
同時に「心の教育」も忘れずに・・・
最後までお読みいただき有り難うございました。
感謝。
漢仁